スポーツや日常生活の中で、不意に身体をどこかにぶつけてしまい、痛みや腫れ、内出血を起こした経験はありませんか?
これは「打撲」と呼ばれるケガで、誰にでも起こり得る身近なものです。
しかし、「ただの打撲だから」と軽視してしまうと、回復が遅れたり、思わぬ不調につながったりすることもあります。
この記事では、突然の打撲に落ち着いて対応できるよう、初期対応から早期回復、再発防止のためのセルフケアまでを専門家の視点から解説します。
適切な対処法を知り、日々の習慣を見直すことで、打撲からの早期回復とケガの予防に役立てていただければ幸いです。

院長からのメッセージ
柔道整復師
元力士「鷲の海」として、
私自身も怪我と治療院巡りに苦しみました。
だから、あなたの痛みが分かります。
「もう治らない」と諦める前に、
ぜひ一度、ご相談ください。
私が、あなたの「治療院巡りの最後」になります。
打撲の初期対応と早期回復のポイント
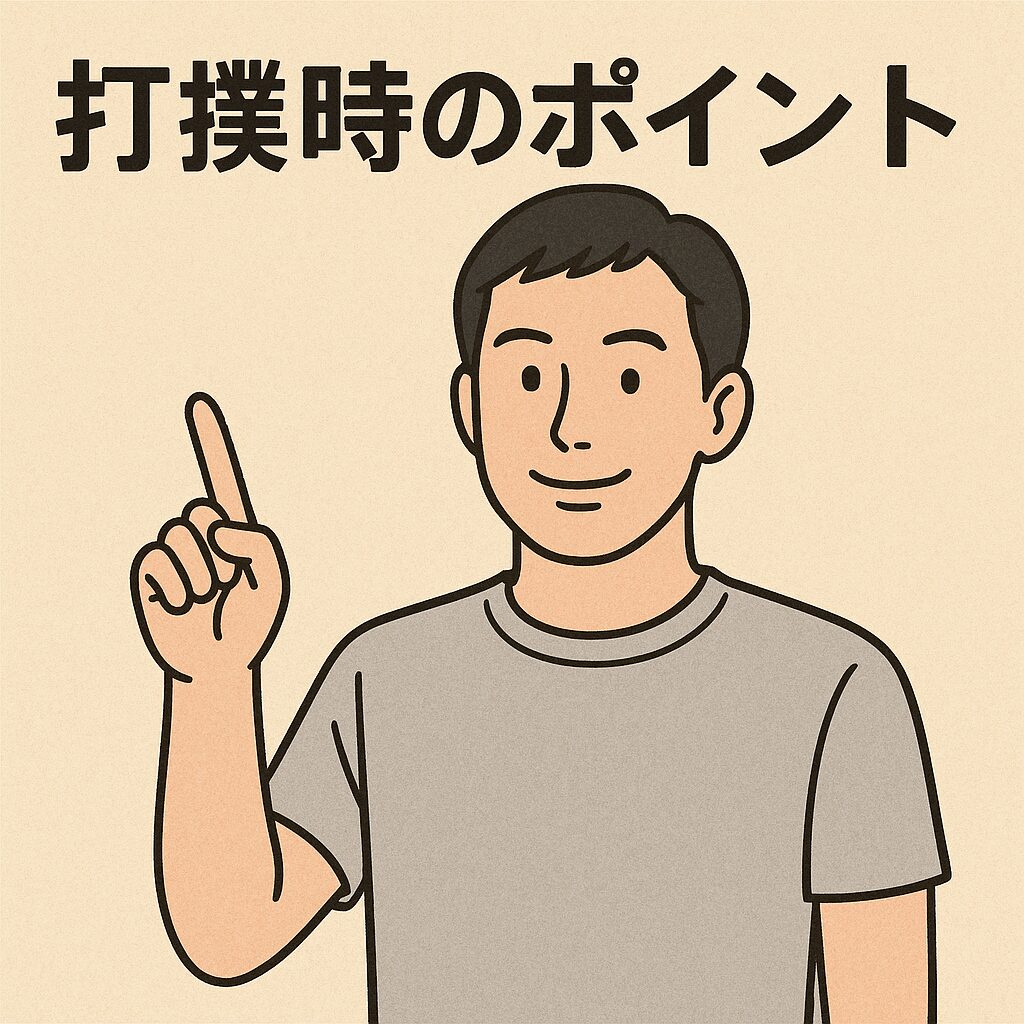
打撲をしてしまった際は、焦らずに適切な初期対応をすることが重要です。
一般的に、打撲の初期対応には「RICE(ライス)処置」が推奨されます。
これは、以下4つの処置の頭文字を取ったものです。
- Rest(安静): まずは患部を動かさず安静に保ちます。
無理に動かすと、腫れや痛みが悪化する可能性があります。 - Ice(冷却): 氷や保冷剤を使って、患部を冷やします。
冷却することで、内出血や腫れを抑える効果が期待できます。
氷のうをタオルで包むなどして、直接皮膚に当てないように注意しましょう。 - Compression(圧迫): 患部を弾性包帯などで適度に圧迫します。
圧迫により、腫れの拡大を防ぐことができます。
ただし、締め付けすぎると血行不良の原因となるため、注意が必要です。 - Elevation(挙上): 患部を心臓より高い位置に上げます。
挙上することで、重力により血流が抑制され、腫れを軽減する助けとなります。
これらの初期対応を適切に行うことで、炎症を抑え、早期回復に繋げることが期待できます。
痛みが強い場合や、腫れがひどい場合は、速やかに医療機関や専門家へ相談することをお勧めします。
練習環境や季節の変化が身体に与える影響
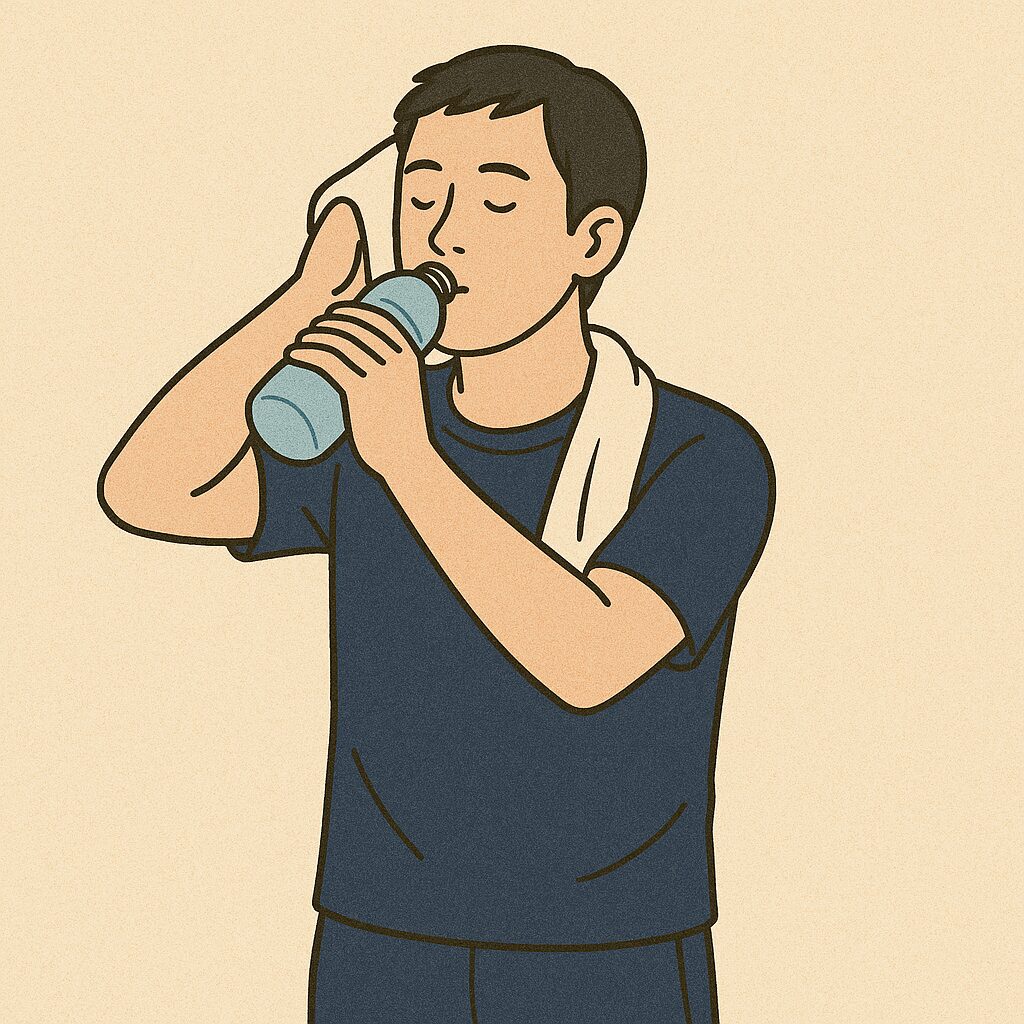
スポーツをする方は、練習環境や季節の変化が身体に影響を与えることを知っておくことも大切です。
例えば、寒さが厳しい時期は筋肉が硬直しやすく、ケガのリスクが高まります。
また、夏の暑い時期は脱水症状に陥りやすく、筋肉のけいれんやパフォーマンスの低下を招くことがあります。
このような環境の変化に対応するためには、適切な準備運動とクールダウンが不可欠です。
寒い時期にはいつもより入念に身体を温める、暑い時期にはこまめな水分補給を心がけるなど、環境に合わせた対策を取り入れることが、打撲だけでなく様々なケガの予防に繋がります。
再発防止のために知っておきたい体づくりのコツ

一度打撲をしてしまうと、同じ箇所を再び痛めてしまうことがあります。
ケガの再発を防ぐためには、日頃からケガをしにくい身体づくりを心がけることが大切です。
具体的には、以下の3つのコツを意識してみましょう。
- 柔軟性の維持:
関節や筋肉の柔軟性を保つことで、可動域が広がり、不意な力が加わった際にもケガをしにくくなります。
日々のストレッチを習慣にしましょう。 - 筋力バランスの改善:
身体の左右の筋力に差があると、片側に負担が偏り、ケガの原因となることがあります。
全身の筋力バランスを意識したトレーニングを取り入れることが大切です。 - 正しい姿勢の意識:
悪い姿勢は身体の歪みを引き起こし、特定の部位に過度な負担をかけます。
デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続ける場合は、時々休憩を挟み、姿勢を正すことを意識しましょう。
これらの体づくりのコツは、打撲の予防だけでなく、腰痛や肩こりといった慢性的な不調の改善にも役立ちます。
疲労をためない日常ケアと来院のタイミング

打撲からの回復を早め、再発を防止するためには、日々の疲労をためないことも重要です。
疲労が蓄積すると、筋肉の柔軟性が失われたり、集中力が低下したりして、ケガをしやすい状態になります。
- 疲労回復のヒント:
十分な睡眠、バランスの取れた食事、湯船に浸かるなど、日々の疲れを癒す習慣を取り入れましょう。
疲労をためないことが、身体の不調を未然に防ぐことに繋がります。
来院のタイミング:
打撲をしてから数日経っても痛みが引かない、腫れがひどくなる、内出血が広がる、といった場合は、放置せずに専門家に相談することをお勧めします。
また、「いつもこの部分を打ってしまう」「同じようなケガを繰り返してしまう」
といったお悩みも、身体の歪みや癖が関係している可能性があります。
その際は、一度専門家にご相談いただくことをお勧めします。
いつものクセを見直してケガを予防しよう

打撲の原因は、不運な事故だけでなく、日々のちょっとしたクセや習慣に隠されていることもあります。
例えば、いつも同じ側の肩にカバンをかける、座る時に足を組む、といった無意識のクセが身体の歪みを引き起こし、ケガをしやすい状態を作っている可能性があります。
ご自身の日常生活を振り返り、身体に負担をかけているかもしれないクセを見直してみましょう。
小さな意識の変化が、大きなケガの予防に繋がることがあります。
まとめ
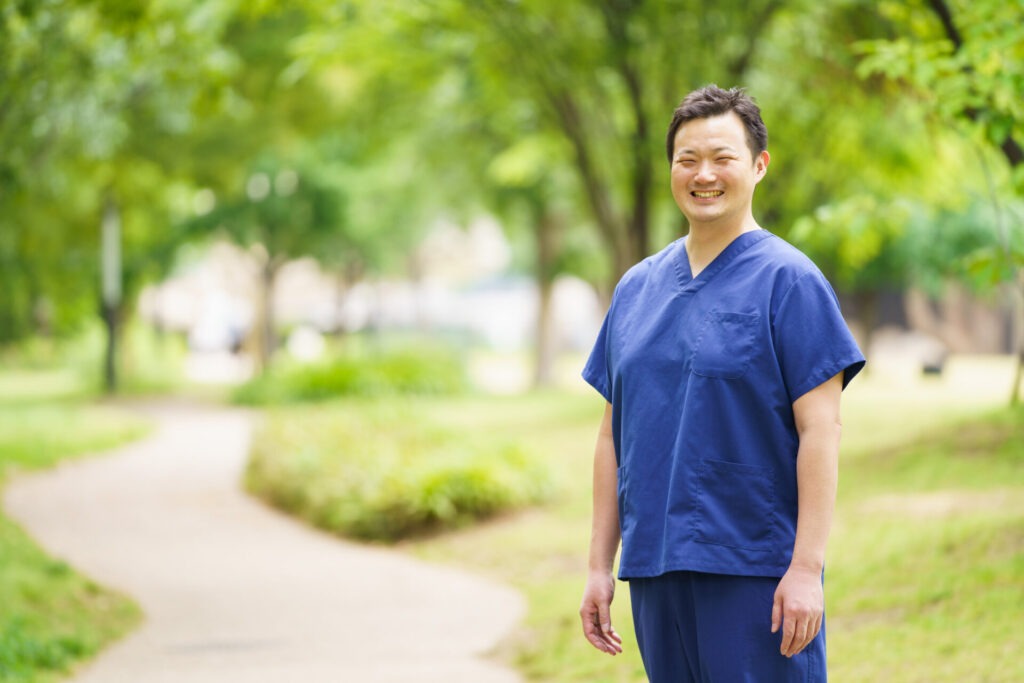
この記事では、スポーツや日常生活での打撲に対する初期対応から、再発予防のための身体づくりについて解説しました。
突然の打撲に慌てず、適切な初期対応を行うこと、日々の習慣を見直してケガをしにくい身体をつくることが大切です。
もし、痛みが続く場合や、ケガを繰り返してしまう場合は、一人で悩まず専門家に相談されることをお勧めします。
健湧接骨院では、打撲の痛みに対する専門的な施術や、再発予防のための生活指導も行っております。
お身体のことでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
【柔道整復師 江本 直樹 監修】
その他の記事
健湧接骨院・公式LINE
ご不明な点がありましたら、こちらからお問い合わせください。
↓ ↓






